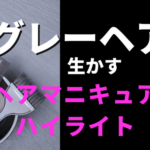2020年、現在ヘアカラーをしている人の人口は1855万人ともいわれています。(参考:理美容ニュース)
私のサロンのお客様の中でも、カラーをしていない素髪の方は数人です。
10〜20代の方たちの中ではブリーチを駆使した多様なデザインカラーが定着してきており、今や白髪が気になり始める40代以降の世代にも広がっています。
このページではアルカリカラーとかぶれ、アレルギーについて、パッチテストの方法についても合わせてご紹介します。
アレルギー性接触皮膚炎と一時的接触皮膚炎の違い
一般的に「かぶれる」というと、皮膚に何かしらの炎症や湿疹などが現れ、痒かったりヒリヒリしたりするようなことを指す場合が多いですよね。
カラーのアレルギー症状の例

実は、私は幼少期から喘息とアレルギー体質を持っていて4〜5歳ころ肺炎になりかけたりよく発作を起こしていました。
成人して美容師になったあとも薬剤のアレルギー反応との共存の日々でした。
まず、ヘアカラーに対してのアレルギー症状の例をあげます。
私も頭皮にカラー剤がつくと同様の反応が出ます。
・そのかゆみが酷く、数日、1週間くらい続く。ひどいときは掻きすぎて頭皮から汁が出てくる。蕁麻疹が出る場合も。皮膚が盛り上がってくる。
・頭だけではなく、洗い流す際に耳の裏や首筋、フェイスラインについた溶液にも反応。耳が焼けるように痒くなり、首やフェイスラインも腫れてくる。
これらは、ジアミンアレルギーなど、カラー剤の成分の中のなにかにアレルギー反応を起こしている人に起こる症状の例です。私もすべて当てはまります。(ジアミン以外の成分だけとは限りません)
カラーの一時的接触皮膚炎の例
次にアレルギー性のものではなく、一時刺激性皮膚炎の主な症状をあげます。
・徐々に症状がおさまってくる。(1〜数日くらい)
・接触した部位だけ反応が出るケースが多い。
現代人はきれい好きでシャンプー回数も多いため、頭皮の皮脂が洗い流され過ぎている方も少なくありません。そういった頭皮は、保護バリア機能が低下しているとカラーのアルカリ剤や過酸化水素などで刺激を感じやすくなることがあります。
こんなときはすぐ病院へ!重篤なアレルギー症状
まれですがカラー剤を塗布してすぐに反応が出ることがあります。もし、セルフカラーをしていてこんな症状が出たらすぐヘアカラーを洗い流し、医療機関を受診してください。

こんな時はすぐ病院へ!アナフィラキシーショックで起こる症状の例
ヘアカラー中から30分くらい(即時型のアレルギー症状)でこんな症状が出たら洗い流してすぐ病院へ行きましょう。
呼吸困難
めまい
意識障害
血圧低下など
強い発赤や蕁麻疹
気管支喘息など
アレルギーではなく「しみる」人への簡単にできる対策
ヘアカラーがしみる方は刺激の少ない他のカラー剤に変える方法が一番良いのですが、できないときは以下の方法をお試しください。
・カラーする1〜2日前から湯シャン(シャンプーを使わない)か、頻度を減らす。
・カラー剤を浮かせて塗布してもらう
しみない対策.1|頭皮の皮脂による保護バリア機能を維持
頭皮の皮脂がシャンプー剤により除去されすぎていると、頭皮の保護バリア機能が弱くなります。
皮脂膜がカラー剤の刺激から頭皮を守ってくれる役割があると言われていますので過剰な洗浄や、脱脂力の強いシャンプーは控えるのがベストです。
しみない対策.2|カラー剤を肌につけないよう浮かせて塗ってもらう
カウンセリング時に敏感肌であることを必ず美容師に伝えましょう。
「肌が弱くしみるので肌につけないで塗ってください」と伝えるのが一番効果的です。
- アレルギーの疑いや敏感体質の方が初めてのサロンに行くときは必ず美容師にそのことを伝えましょう。
- 「頭皮につけないで」「浮かせて」塗ってほしい、とはっきり伝えることが重要です。根本1センチの白髪染めなど頭皮につくリスクがあります。
- 施術前にパッチテストをしてもらうと安心です。(パッチテストは48時間の経過を確認、2回のご来店が必要です。あらかじめサロンに相談するのがおすすめです。)
ヘアカラーでかゆみなどが出た場合の代替カラー
一度反応が出た場合は、無理をして続けるのはよくありません。繰り返すことで顔が腫れる、アナフィラキシーなど重度なアレルギー反応が起こると命に関わることもあります。
染め続けたい人にはヘアマニキュア、化粧品分類のカラーなどに変えるなどの方法があります。(当サロンはノンジアミンカラーの取り扱いはしておりません)
※初回ご予約時にアルカリカラーのパッチテストについての詳細をご案内しております。
市販のカラー剤のパッチテストと同様、美容室で提供する薬剤をご自身で皮膚の状態を確認して判断していただく形になります。
前回のカラー後に少しでも痒みや異変を感じるようでしたら、次回以降は使用を中止します。
化粧品分類のサロンカラーの選択肢
化粧品分類のヘアカラー代替品の例を挙げます。サロンによって取り扱いが違います。
ヘアマニキュア(酸性カラー)
ヘアマニキュアは、髪に入ってメラニン色素を脱色して明るくすることはできませんが、髪表面近くに染料が着色するものです。頭皮に薬剤をつけない塗り方なのがいちばんのメリットです。
またアルカリやジアミン、過酸化水素なども配合されていません。
ただしアルコールにとても過敏な方は様子を見て使うことをおすすめします。
毛髪のダメージも、アルカリカラーと比較すると少ないです。パッチテストは不要です。(体質に合わない場合は使用を中止します)
ヘナ(100%ヘナでジアミンなどの化学物質を含まない高品質なもの)
ヘナって聞いたことがありますか?オレンジ色に染まる、といったイメージを持っている方もいらっしゃると思います。
ヘナを扱っているサロンは非常に少ないです。
利便性や色の表現性からアルカリカラーでのメニュー展開が一般的です。
ヘナの中にはアルカリカラーのように短時間で染まるものや、一回の使用で黒っぽく濃く発色するものがあり、ジアミン系化合物などアルカリカラーに配合されているような発色をサポートする原料がわずかに添加されているケースもあります。
それを理解していて最小限の化学物質を使っていても早くしっかり染まることを望む人には良いのですが、100%ヘナを求めていてアレルギーや皮膚、からだに害の少ないものを求めている人が知らずにこういった商品を使う際には気をつけたいものです。
サロンでヘナを行うときは安全で信頼できるヘナを使用している美容室を選ぶことがかなり重要です。
ヘナはカラーではない
ヘナは自然の植物色素(ローソニア)を利用して染まることをヘアカラーに応用したもので、ヘアカラーではありません。化学物質でできたアルカリカラーなどに比べると、発色に時間がかかりますが、長期的に見るとダメージもなく髪のケア性にはとてもすぐれているのが特徴です。
ヘナは黒い髪を明るくすることはできません。オレンジ色です。
植物にかぶれやすいなどヘナやインディゴに対してアレルギーがある人は使用できません。
ご使用前は必ずパッチテストを行います。
究極のアレルギー対策は染めるのをやめてグレーヘアにすること
今や、グレーヘアにすることはファッションの一部になりました。
染めるのを潔くやめるという決断は誰にでもできることではないのですが、新しい価値観のファッションライフを楽しめることでしょう。
カラーのパッチテストでアレルギー反応をチェックする方法
ご自宅でホームカラー(セルフカラー)をしている人、箱にパッチテストについての注意書きがあるのをご存知ですか?

基本的にアルカリカラー、酸化染毛剤、2剤式カラーなどと書いてあるものは同じ分類ですので使わないようにします。
ヘアマニキュア、カラートリートメントなど化粧品タイプのカラー剤で対応したほうがかぶれるリスクが少ないです。
①使う薬剤を少量腕の内側など皮膚の薄いところに塗る。綿棒を使うと塗りやすいです。
②10円玉くらいの面積に塗って、乾くまで放置。(乾ききったら軽く水で湿らせたティッシュで拭き取ってOK、赤くなるほどこすらないで)
③直後、赤みが無いかチェック。ここで痒かったり赤かったりしたら染めるのはやめましょうというサインです。
④なんともなかったら24時間、48時間後もチェックして以上なしならすぐ染めてOK。
※絆創膏などで覆う方法も聞いたことがありますが、絆創膏にかぶれる反応が出た場合、混同されやすいので私ははらないやり方にしています。あくまで私の経験からの意見です。
アレルギーが有る人の大抵の場合は塗布して乾くまでの一回目のチェックですでに反応が出るパターンが多いです。私も、1時間以内にかゆみと赤みが出ることが多いです。下の写真はわたしがパッチテストをしているところです。インディゴ染料という植物性の染料を調べました。

カラー剤を塗った直後。

1時間後、薬剤が乾いて拭き取ったあと。発赤とかゆみが。
実はこの数日前にインディゴでヘアカラーをしたところ若干かゆみを感じたため、「多分アレルギーだな」と予感してチェックしました。結果、少し反応が出ました。
ヘナ100%の方は問題なしでした。このように、化学物質であるか、植物原料かは関係なくまれにアレルギー反応は起こりえます。また同じ薬剤やハーブでも全く反応が出ない人も大勢いらっしゃいます。
いちばんのアレルギー対処法は原因物質に接触させないこと
食べ物にしても、カラー剤にしてもアレルギー反応を起こさせない最良の方法はアレルギー原因物質に接触しないことです。残念ながら薬などで治るものではなく、からだが異物の侵入を必死に拒む反応なので、アレルギーが起こる原因物質を取り入れないことが対策になります。私も皮膚科や呼吸器科でたびたび医師に言われます。
アレルギーに関しては美容師によって情報量と経験値、対処法の差がありますので信頼できる美容師のもとでサロンカラーをするのが安心です。
出典:日本ヘアカラー工業会のサイト、ヘアケアマイスターBOOK、